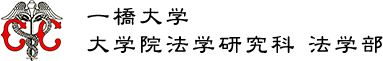第20巻
| 第20巻 第3号(2021年11月) | |
|---|---|
| <論説> | |
| 刑事手続における通信秘密の保護 ― 弁護人の効果的援助の保障と正確な事実認定― |
葛野 尋之 |
| 中国の党政機構改革と「法治」 | 但見 亮 |
| オランダ消費者・市場庁による 新しいガイドラインの立案について ― 競争法における持続可能性の合意に関する機会― |
柳 武史 |
| 物理的幇助犯における因果関係の判断枠組み(1) | 酒井 智之 |
| 議会解散権の日英比較 ― 議会任期固定法は日本の範例たりうるか― |
柴田 竜太郎 |
| 超過議席と選挙の平等 ― ドイツ連邦憲法裁判所判決と それを巡る近年の学説を中心に― |
小林 宇宙 |
| 国際比較を通じた ESG 投資の拡大要因 ― 推進主体に着目して― |
御代田 有希 |
| 『ノモカノン』検討序説 | 渡辺 理仁 |
| <研究ノート> | |
| 監査等委員会制度の実効性に関する一考察 ― 経営者評価機能からのアプローチ― |
顧 馨怡 |
| <書評> | |
| 北村幸也著『裁判と法律のあいだ― ドイツ憲法の視角から―』 (成文堂、2020 年) |
渡辺 康行 |
| <翻訳> | |
| 瑕疵ある国家監督に対する国家責任 | マティアス・コルニルス(473) (訳 吉岡 郁美) (監訳 下山 憲治) |