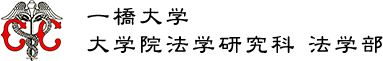第19巻
| 第19巻 第1号(2020年3月) | ||
|---|---|---|
| 森村進先生 退職記念 | ||
| 献辞 | 青木人志 | |
| 私の歩んできた法哲学研究の道 | 森村進 | |
| 中国の法概念について考える ―「新時代」の「法治」が示すもの― |
但見亮 | |
| 室町幕府の法概念に関する覚書 | 松園潤一朗 | |
| 人権論のパラドクスと抵抗への権利 ―コスタス・ドゥジナスの批判法学― |
関良徳 | |
| 法の一般性 | 鳥澤円 | |
| シモンズの権利基底的な政治的責務論とリバタリアニズム | 山本啓介 | |
| 強制性と法の概念 ―フレデリック・シャウアーのThe Force of Law― |
三浦基生 | |
| アダム・スミスの所有権論 ―分析と再構成― |
太田寿明 | |
| 森村進名誉教授 略歴 | ||
| 森村進名誉教授 主要研究業績 | ||
| <論説> | ||
| 商法の構造と基軸概念 | 酒井太郎 | |
| アメリカにおける判決前調査の歴史的変遷 | 吉村千冬 | |
| ドイツ連邦憲法裁判所の「三段階説(Drei-Stufen-Lehre)」・再考 ―分析の対象・視角を変えるなどして― |
高橋和也 | |
| <研究ノート> | ||
| 罪証隠滅防止を目的とする起訴前勾留の経済学的分析 | 大角洋平 | |
| <判例研究> | ||
| 土地改良区が河川法23 条の許可に基づいて取水した水が流れる水路への第三者の排水により当該水路の流水についての当該土地改良区の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断に違法があるとされた事例 令和元年7 月18 日第一小法廷判決(平成30 年(受)533 号他, 以西土地改良区対Y1 他,使用料請求事件)裁判所ウェブサイト |
土井翼 | |