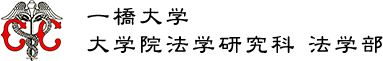第1巻
| 第1巻 第3号(2002年11月) | |
|---|---|
| <論説> | |
| 国立大学法人化と教職員の地位 ――「非公務員型」の意義と課題(下) |
盛 誠吾 |
| 財産関係の改革と現代化 ――2002年改正法 |
小野 秀誠 |
| 代表の概念に関する覚書(2) ――P・ロザンヴァロンによるフランスの民主主義の歴史から |
只野 雅人 |
| 『トレヴー事典』の東アジア関係項目 | 小関 武史 |
| 刑罰論から見た量刑基準(3・完) | 本庄 武 |
| 加藤高明像の再構築 ――政党政治家とビジネスマンとしての視点から |
王 平 |
| DNA証拠の許容性 ――Daubert判決の解釈とその適用 |
徳永 光 |
| ドイツ法における「契約結合(Vertragsverbindungen)問題 ――契約の一体性と一部無効・一部解除問題 |
中川 敏宏 |
| フランス公法と反セクト法 | 中島 宏 |
| <書評> | |
| 塩野谷祐一『経済と倫理 福祉国家の哲学』 | 森村 進 |
| 第1巻 第2号(2002年6月) | |
|---|---|
| 中国憲法学の動向と課題 | 韓 大元 (訳、解説:西村 幸次郎) |
| <論説> | |
| 新成年後見制度と国際司法 | 横山 潤 |
| 国立大学法人化と教職員の地位 ――「非公務員型」の意義と課題(上) |
盛 誠吾 |
| インドシナ諸国における民法典の整備と開発 ――民事法整備支援への参加を通じて感じたこと |
松本 恒雄 |
| 反グローバリゼーションの諸位相 | 山田 敦 |
| 刑罰論から見た量刑基準(2) | 本庄 武 |
| ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体(ECSC)の成立をめぐる国際政治過程 1950―51年 ――仏・米・西独関係を中心に |
山本 健 |
| ドイツ競争制限禁止法及び不正競争防止法における結合取引の規制について | 川原 勝美 |
| <研究ノート> | |
| リバタリアニズムと犯罪被害者救済 | 森村 進 |
| <資料> | |
| 『国際法先例彙揖(10)同盟』解題(2・完) | 佐藤 哲夫 |
| 第1巻 第1号(2002年3月) | |
|---|---|
| 発刊の辞 | 山内 敏弘 |
| <法学部創立50周年記念講演> | |
| 司法制度改革とこれからの法学教育 | 竹下 守夫 |
| <論説> | |
| 生命権と死刑制度 | 山内 敏弘 |
| 二重効と請求権競合 | 小野 秀誠 |
| 証書による証明と意思表示理論 ――ウィグモアの証拠法を契機に |
滝沢 昌彦 |
| 代表の概念に関する覚書(1) ――P・ロザンヴァロンによるフランス民主主義の歴史から |
只野 雅人 |
| 晩年のエミリー・ケンピン=シュピーリ | 屋敷 二郎 |
| 日独における電磁波規制の動向 | 戸部 真澄 |
| 刑罰論から見た量刑基準(1) | 本庄 武 |
| Rahmenvertag〈枠契約〉の史的変遷とその現代的意義に関する一考察 | 寺川 永 |
| <資料> | |
| 『国際法先例彙揖(10)同盟』解題(1) | 佐藤 哲夫 |