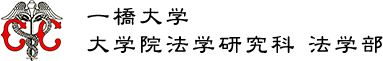第17巻
| 第17巻 第3号(2018年11月) | |
|---|---|
| 佐藤哲夫先生 退職記念 | |
| 献辞 | 中西 優美子 竹村 仁美 |
| 一般国際法の強行規範の法的効果 | 川﨑 恭治 |
| 国際海洋法裁判所暫定措置における緊急性の要請 | 田中 嘉文 |
| 欧州人権裁判所のEU法に対するスタンス -裁判所意見2/13以降も「同等の保護」の推定原則は維持されるか?- |
中西 優美子 |
| 国際司法裁判所判決の履行に関する一考察 -最近の判例を中心に- |
石塚 智佐 |
| 国際刑事裁判所の正統性と実効性 | 竹村 仁美 |
| 国際組織の「事後の実行」再考 -ILC結論草案を手がかりに- |
丸山 政己 |
| 国連安保理決議と関連してEUが行う金融制裁に対するEU司法裁判所の審査基準の一貫性 | 柳生 一成 |
| 「組織法としての解釈理論」に関する一考察 | 佐藤 量介 |
| 国際組織法から観た自衛権 -「テロリストに対する自衛権」に関する一考察- |
近藤 航 |
| 国際法秩序の特性に基づく国際法人格の要素 | スキファノ・ アドリアン |
| 国際組織に対する加盟国の協力義務 | 中村 江里加 |
| 最終講義録:国際法研究の40年と国連安全保障理事会 | 佐藤 哲夫 |
| 佐藤哲夫名誉教授 略歴 | |
| 佐藤哲夫名誉教授 研究業績目録 | |
| <論説> | |
| 犯人識別供述の信用性 | 青木 孝之 |
| 弁護人による接見時の情報通信機器の使用をめぐる法的問題 | 葛野 尋之 |
| ドイツ 連邦憲法裁判所の「三段階説 (Drei-Stufe n-Lehre) 」 -「比例原則」・「 機能法的アプローチ」との結びつきを中心に- |
高橋 和也 |
| 一般法律と比例原則研究序説 | 菅沼 博 子 |
| 第三セクターと地方議会 -議会による情報請求権の行使のあり方をめぐって- |
宮森 征司 |
| 人民のための違憲審査 -ポストとシーゲルの民主的立憲主義論について- |
川鍋 健 |
| 第17巻 第2号(2018年7月) | |
|---|---|
| 山田洋先生 退職記念 | |
| 献辞 | 野口 貴公美 |
| 部分開示と情報の単位 -最高裁判所の裁判例の再考- |
高橋 滋 |
| 普通選挙と選挙裁判所 -フランスにおける投票の真正(sincérité)の概念をめぐって- |
只野 雅人 |
| 韓国における環境責任法の役割と展望 | 金 到煥 |
| 「難民を認定する行為」の行政法学的分析 | 野口 貴公美 |
| 台湾における環境影響評価法制度の研究 -実体法の観点から- |
賴 宇松 |
| 国家賠償訴訟における反射的利益について | 戸部 真澄 |
| 統合的事業案許可の制度設計 -環境法典独立専門家委員会による構想- |
川合 敏樹 |
| インフラ事業の立地計画とその展開 -ドイツの国土整備計画を素材として- |
山本 紗知 |
| 電気自動車の普及促進策と法的課題 | 髙田 実宗 |
| 山田洋名誉教授 略歴 | |
| 山田洋名誉教授 著作目録 | |
| <講演> | |
| 裁判官とは何者か? -その実像と虚像とのはざまから見えるもの- |
千葉 勝美 |
| <論説> | |
| 人民の、人民による、人民のための憲法 -アキル・リード・アマールの憲法論から- |
川鍋 健 |
| 在日米軍政策におけるアクター間の合意過程 | 辛 女林 |
| <研究ノート> | |
| 中国の憲法改正と監察法の制定 -「法治国家」への前進になるか- |
王 雲海 |
| <判例研究> | |
| 外国国家が発行した円建て債券に係る償還等請求訴訟につき、当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして原告適格を有するとされた事例(最高裁平成 26 年(受)第 949 号:債券償還等請求事件)(最高裁平成 28 年 6 月 2 日第一小法廷判決、民集 70 巻 5 号 1157 頁) | 八木 敬二 |
| 第17巻 第1号(2018年3月) | |
|---|---|
| <論説> | |
| 準民主主義国議会の議事録の実証分析 ―ナイジェリア上院の政治的暴力への反応を例に― |
大林 一広 飯田 連太郎 ジョナサン・ルイス |
| テロリズムに対抗する予防的警察活動と比例原則(2・完) ―je-desto公式と、法的概念としての「安全」― |
小西 葉子 |
| 生存権の自由権的側面による最低生活保障 ―ドイツ連邦憲法裁判所の判例を素材として― |
松本 奈津希 |
| <研究ノート> | |
| 台湾著作権法における貸与権とその消尽規定について | 林 季陽 |
| 捜査法上の処分に対する経済学的分析 ―Orin S. Kerrの論文を参照して― |
大角 洋平 |