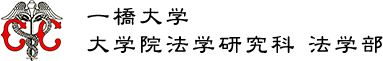第16巻
| 第16巻 第3号(2017年11月) | |
|---|---|
| <論説> | |
| 平成28年改正刑訴法等のアセスメント | 青木 孝之 |
| M&A取引と差止め(2) | 玉井 利幸 |
| 平安時代における知行と「理」の概念 | 松園 潤一朗 |
| 強盗致死傷罪の要件に関する判例及び裁判例の分析的検討 | 吉野 太人 |
| 関係的権利論における応答の概念 ―「他者」としての子供の人権論― |
大西 健司 |
| 経済再建のための保守合同 ―保守政党の再編過程における岸信介の認識と行動の再検討― |
長谷川 隼人 |
| 動物実験に関するEU法の展開 ―化粧品のための動物実験を中心に― |
本庄 萌 |
| 中世カノン法の欠席手続 ―『グラティアヌス教令集』C.3q.9を素材として― |
川島 翔 |
| 被告人の自己負罪拒否特権の発達過程 ―権利の実質化と刑事手続構造への影響という視点から― |
方 海日 |
| テロリズムに対抗する予防的警察活動と比例原則(1) ―je-desto公式と、法的概念としての「安全」― |
小西 葉子 |
| 第16巻 第2号(2016年7月) | |
|---|---|
| <論説> | |
| 室町幕府雑務沙汰の形成と「借書」の効力 | 松園 潤一朗 |
| 弁護人の効果的な援助を受ける権利 | 田鎖 麻衣子 |
| 「和解的執行(執行ADR)」再考 ―ドイツ法・中国法の実務運用を手がかりとして― |
史 明洲 |
| <研究ノート> | |
| 韓国における死刑の執行停止とその後の刑事政策 | 藤原 凜 |
| <判例研究> | |
| 国際刑事裁判所において初めて有罪の自認についての公判手続が実施され、世界遺産の破壊行為につき戦争犯罪の成立を認めた事例 ―The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi(2016年9月27日 国際刑事裁判所第一審裁判部判決及び刑の言渡し) |
竹村 仁美 |
| 第16巻 第1号(2017年3月) | |
|---|---|
| <論説> | |
| 刑事手続における科学鑑定の現状と課題 -鑑定人の地位論を中心に- |
本庄 武 |
| 国家理論における一元性と多元性(2・完) -カレ・ド・マルベール第三著作再読- |
門輪 祐介 |
| ドイツにおける信条冒冒涜罪正当化の試みの憲法学的一考察(2・完) -宗教をめぐる「情念」の保護のための巧知?- |
菅沼 博子 |
| 近代フランス憲法思想の再構成(2・完) -19世紀前半期及び第三共和制初期を中心に- |
水林 翔 |
| テクスト解釈とその目的-ジャック・M・バルキンの「生ける原意主義」、そして「憲法の救贖」という物語について- | 川鍋 健 |
| <講演> | |
| 最高裁判所判事になったマチ弁の随想 | 山浦 善樹 |
| 法曹倫理と刑事弁護についての考察 | マイケル・タイガー (訳:村岡 啓一) |
| ドイツ刑事手続における弁護人の機能と地位 -今日までの論争- |
ヴェルナー・ ボイルケ (訳:加藤 克佳 =辻本 典央) |