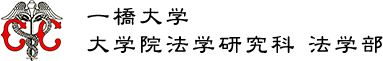「少年法は厳罰主義を採用したと解すべきか―法解釈論への招待を兼ねて」
本庄武(2005年4月)
1 はじめに
本稿は、これから法律学を学ぼうとする学生の皆さんを対象に、少年法20条2項を素材として、法解釈論とはいかなるものか、なぜ法律を解釈することが必要なのかについて、筆者なりの考えを提示しようとするものである。当該条文は、少年すなわち20歳未満の者に対していかなる場合に刑罰を科すべきかを規定した条文である。大学で法律学を学び始める人の大部分は少年法の適用対象者であろう。読者1人1人が自分が犯罪を犯した場合にどのような処分を受けるべきかを考えながら、本稿を読み進めていってもらいたい。
2 法解釈論の必要性
大学の法学部で講義される科目のうち、憲法、民法、刑法等の実定法科目においては個々の条文を取り上げて、その条文の意味を明らかにすることが内容の大部分を占める。この条文の意味を明らかにする作業を解釈論という。法律の条文はしばしば難解な言葉で書かれているが、所詮は日本語である。必要に応じて辞書を引きながら読んでいけばその意味は自ずと明らかになるのではないかと思われる方も多いだろう。それなのに、なぜ解釈論が必要なのであろうか。確かに通常の文章と同じように読めば足りる場合も多い。しかしそれでは済まない場合が存在するのである。そのため解釈の手法が用意されている。解釈手法の分類は人により様々であるが、①文理解釈(言葉の通常の意味に即した解釈)、②体系的解釈(法律の他の規定やより上位の法律、特に憲法との関係などから判断する解釈)、③立法者意思による解釈(法制定時の立法者の意図を歴史的に明らかにし、それに従って行う解釈)、④目的論的解釈(法の真の目的を探り、それに即してする解釈)等がある。複数の手法が複合的に用いられることもある(探り出した法の真の目的が憲法の理念に合致していた場合など)。
なぜ解釈論が必要とされるのか、刑法を素材に見てみよう。
まず第1に法律は社会の中で生じるであろう様々な事象を法的に規律することを目的としているが、あらゆる事象を想定してそれに対応する条文をおくことは煩雑であるだけでなく不可能である。例えば刑法39条1項は、「心神喪失者の行為は罰しない」と規定しており、これは責任無能力の規定であるとされている。しかし、いかなる場合が心神喪失に該当するかどうかは何も規定していない。罪を犯す時の精神状態は千差万別であり、しかも精神医学的判断を踏まえなければ答えの出せない問題である。しかも精神医学の発展と共にその判断は常に変化し続ける。そこで刑法はこの問題を解釈に委ねたものと考えることができる。
第2に、立法当時予想し得なかった新たな事態が発生することがある。例えば刑法199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」として殺人罪を規定する。この規定の適用範囲を確定させるためには、人類という生命体がいつ「人」になり、いつ「人」でなくなるかをはっきりさせなければならない。この後者の問題について、長い間、心臓が停止すれば人は死亡するのだと考えられてきた。しかし医学の発展により、心臓はなお動いているが、脳が活動を停止した脳死という状態が出現し、この状態を人の死に含めるか否かについては刑法の解釈に委ねられることになった。これは脳死状態の者からの臓器摘出の法的評価に絡みなお争われている問題である。
第3に、立法当時学説上争いがある問題について、その解決を将来の解釈に委ねる場合がある。例えば刑法36条は正当防衛としてなされた行為は罰しない旨を規定している。それではAがBを銃で射殺したがその時たまたまBもAを射殺しようとして銃を構えていたが、Aの銃弾が命中したためBは殺害を遂げることができず、死亡してしまったという場合は正当防衛と言えるであろうか(これは、偶然防衛といわれて議論されている問題である)。学説上、正当防衛には、防衛をする意思が必要か否かにつき争いがあり、この場合肯定説では違法に、杏定説では適法になる。この問題について仮に刑法に「防衛の意思により」と明示されていれば、争いの余地はなくなる。しかしこれは刑法における違法性の本質をどのように理解するかという根本問題と深く関わっているため、容易に決着をつけることができない問題である。1995年の刑法口語化のための改正の際、立法者は「防衛するため」という暖味な文言を用い、いずれの立場からの解釈も可能であるようにして(否定説では結果的に防衛に役立っ行為であればよいと解する)、決着を将来の学説に委ねたと考えることができる。
第4に、他の条文との関係である条文の適用範囲を限定すべき場合がある。例えば刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する」として、窃盗罪について規定している。この条文の解釈にあたり、判例と多くの学説は条文に書かれていない不法領得の意思という主観的要件を要求する。その理由の一つとして、刑法261条が「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定していることとの関係が問題となる。刑法は人の物を盗む行為を、他人の財産を自分のものとして利用するというより悪質な動機に基づいている等の理由により、人の物を壊す行為よりも重く処罰している。そうすると、人の物を壊すために盗む行為はもともとの考え方からすれば重く処罰する必要のない行為ということになる。そのため、窃盗罪の成立には「人の物を経済的用法に従って利用・処分する意思」(不法領得の意思)が必要であるとして、この場合を窃盗罪の適用範囲から除外するのである。
第5に、条文を言葉の本来の意味で適用した場合に不合理な結論が生じるため、それを回避する必要がある場合がある。これには事実上条文の文言を無視するような結果となりうる場合もある。例えば刑法174条は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」として公然わいせつ罪を規定している。通説は、わいせつな行為は公衆の面前で行うべきではないという健全な性的風俗が本罪で保護されていると理解し、「公然性」とは、不特定または多数人が認識できる状態のことであると解する。これに対して、見たいと思う人の前であればわいせつな行為をしても何の被害も発生していないとして、本罪を見たくない自由を保護する犯罪であると理解する有力説がある。この学説では「公然性」を見たくない人々の面前と解釈することになる。この解釈は「公然性」の文言からはやや苦しいが、実質的な考察により不合理な結論を回避しようとする例である。
以上は例示に過ぎないが、こういった様々な事情からよりよい法の運用を目指して法解釈が行われるのである。条文の文言は解釈を絶対的に規定するものではないという認識を持っことが重要である。
※抜粋(続きはリンク先のPDFで読めます):本庄武(2005)「少年法は厳罰主義を採用したと解すべきか―法解釈論への招待を兼ねて」一橋論叢,133巻4号,435-458頁