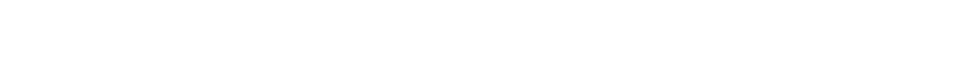発刊の辞
山内敏弘
一橋大学大学院法学研究科では、この度、研究紀要『一橋法学』を刊行することになった。ここに、その創刊号をお届けすることにする。一橋大学では、従来、全学共通の研究誌として『一橋論叢』があり、同誌が年2回法学部特集号を組んで法学研究科の教官や大学院生が寄稿できるようにしてきた。また、その他に原則として年1回刊行の『一橋大学研究年報 法学研究』があり、これに主として法学研究科の教官が研究成果を発表してきた。ただ、これだけでは、法学研究科の教官の研究成果を発表する研究誌としては不十分であり、法学研究科の紀要の刊行の必要性がかねてから指摘されてきた。
例えば、初代法学部長を務められた田中誠二名誉教授は、本学創立百周年を記念して開かれた座談会「法学部の草創期を顧みて」において、1951年の法学部設立当初から法学部独自の研究雑誌を出したいという希望を強くもっていたことを述べている(-橋大学学園史刊行委員会編『一橋大学学問史』1986年)。それが実現できなかった理由として、同名誉教授は、当時にあっては法学部のスタッフの数が少なかったこと、財政的な問題があったこと、そして法学部が独自の雑誌を出すことに対する抵抗かあったことなどをあげているが、これらの障害は、その後、少しずつ解消されるようになってきた。法学研究科のスタッフ数は、創立当初の17名に比べたならは、現在は52名(現員)になっているので、執筆者に困ることは基本的になくなった。財政面でも、かつてと比較すれば、法学研究科としても少しは余裕ができてきた。
問題は、社会科学の総合大学を掲げ、単科大学の歴史をもつ本学で研究科独自の紀要を刊行する意味かあるのかという点であるが、法学研究科の教官や院生の研究発表の機会をこれまで以上に確保する必要があること、法学部のある大学のほとんどでは法学部独自の紀要を刊行していることなどに照らせば、本学でもやはり法学研究科の紀要の刊行の必要性があるというのが、法学研究科教授会の大方の意見であった。昨年行われた法学研究科の外部評価(座長・広渡清吾東大教授)でも、「一橋大学全体として総合的社会科学研究を進めるという伝統と両立する形で本研究科独自の機関誌(紀要)を刊行することの重要性が各委員から指摘された」(『一橋大学大学院法学研究科・法学部外部評価報告書』2001年)のである。このような外部評価をも踏まえなから、法学研究科としては、法学研究科の教官や大学院生を主要な執筆者としながらも、他の研究科の教官などにも開かれた紀要の刊行を検討し、学内諸部局とも交渉・協議を重ねてきた。幸いにも、石弘光学長を初めとして学内諸部局の理解と協力を得ることかできて、ここに、法学研究科を中心としつつも、全学に開かれた紀要として『一橋法学』を刊行する運びとなった。長年の念願がかなったことについて、石学長を初めとして学内諸部局の関係者のご理解とご協力に厚く御礼を申し上げたい。なお、この紀要の刊行をもって、『一橋大学研究年報 法学研究』は廃刊することにした。
21世紀を迎えた現在、日本及び国際社会は大きく変動しており、それに伴って、法学や国際関係の研究にも新たな飛躍か求められている。大学をめぐる環境も、国立大学法人化を控えて、大きく変わろうとしている。本学法学部・法学研究科は、これまでにも、「社会科学の総合的研究」を掲げる本学のリベラルな学風の下で多くの研究業績をあげて内外の学界及び社会に多大の貢献をしてきた。このような伝統を受け継ぎながら、しかも新しい時代の変化に対応しながら、自由で創造的な研究活動を真摯に積み重ね、平和的な人類社会の形成と多様な文化の発展に寄与することは、大学に籍を置く者の基本的な責務といわなければならない。新たに刊行されることになった『一橋法学』が、そのような研究活動の成果発表の場として積極的に活用され、内外の学界及び社会に多くの優れた学問的成果を国立の地から発信していくことを心から念ずるものである。
2002年2月
(一橋大学大学院法学研究科長)